
この記事では、吹き抜けのある家のメリットについて解説します。
吹き抜けのある家は、自然光が入り、風通しが改善されるというメリットがあります。また、開放感が溢れる空間にすることが可能です。
ただし、冷暖房効率が低下するおそれがあることや、メンテナンスが難しいことなどのデメリットがあります。吹き抜けのある家を検討する場合は、メリットとデメリットを考慮するのがおすすめです。
本記事では、吹き抜けのある家のメリットとデメリット、おしゃれに仕上げるアイデアについて解説します。ぜひ、参考にしてください。
そもそも吹き抜けのある家とは?
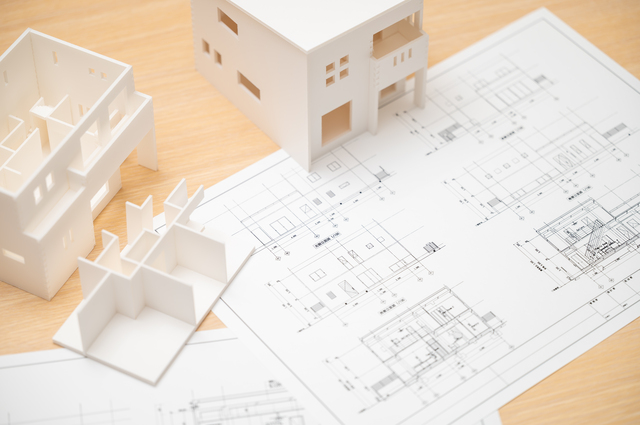
吹き抜けとは、2階以上の建物で、下階の天井と上階の床を設けずに上下階をつなげた空間のことを指します。この構造により空間が広がり、開放感や採光性が向上するのが特徴です。
吹き抜けの高さは、一般的な2階建ての家では約4.5メートルから6メートル程度です。ただし、建物の設計や目的によって異なることがあります。
吹き抜けのある家のメリット

ここからは、吹き抜けのある家のメリットについて解説します。
- 自然光が入る明るい空間になる
- 風通しが改善される
- 開放感が溢れる空間になる
- 家族内のコミュニケーションが活性化する
上記4点について順番に見ていきましょう。
自然光が入る明るい空間になる
吹き抜けがあると、家全体に自然光をたっぷり取り込み、特に天窓や大きな高窓を設置することで、朝から夕方まで太陽光が降り注ぐ明るい空間になります。
この自然光によって、昼間の電気使用量を減らせるため、省エネ効果も期待できます。
風通しが改善される
吹き抜けがあることで、室内の空気の流れがスムーズになり、特に上部に設置した窓や換気口が効果的です。例えば、夏場は温まった空気が自然に上昇し、上部の窓から排出され、下階の窓から涼しい空気が入りやすくなります。
また、湿気が溜まりやすい地域や季節においても、空気の循環が良くなることでカビの発生を抑え、健康的な室内環境を保てます。
開放感が溢れる空間になる
吹き抜けの大きな魅力といえるのが、開放感です。
一般的な天井の高さは約2.5メートルですが、吹き抜けによって大きく超える高さを確保でき、狭いスペースでも広がりを感じさせる効果があります。
特に、リビングや玄関など、家の中心的な空間に吹き抜けを取り入れることで、家全体の印象が大きく変わります。
家族内のコミュニケーションが活性化する
吹き抜けがあることで、上下階が視覚的に繋がり、家族間の距離が縮まります。例えば、リビングから2階の廊下や部屋を見渡せ、階段を使わずに家族と会話が可能です。
また、リビングでくつろぐ家族の気配を感じながら2階で作業したり、逆に2階から1階の様子を見守れるため、家全体が一体感のある空間となります。
吹き抜けのある家のデメリット
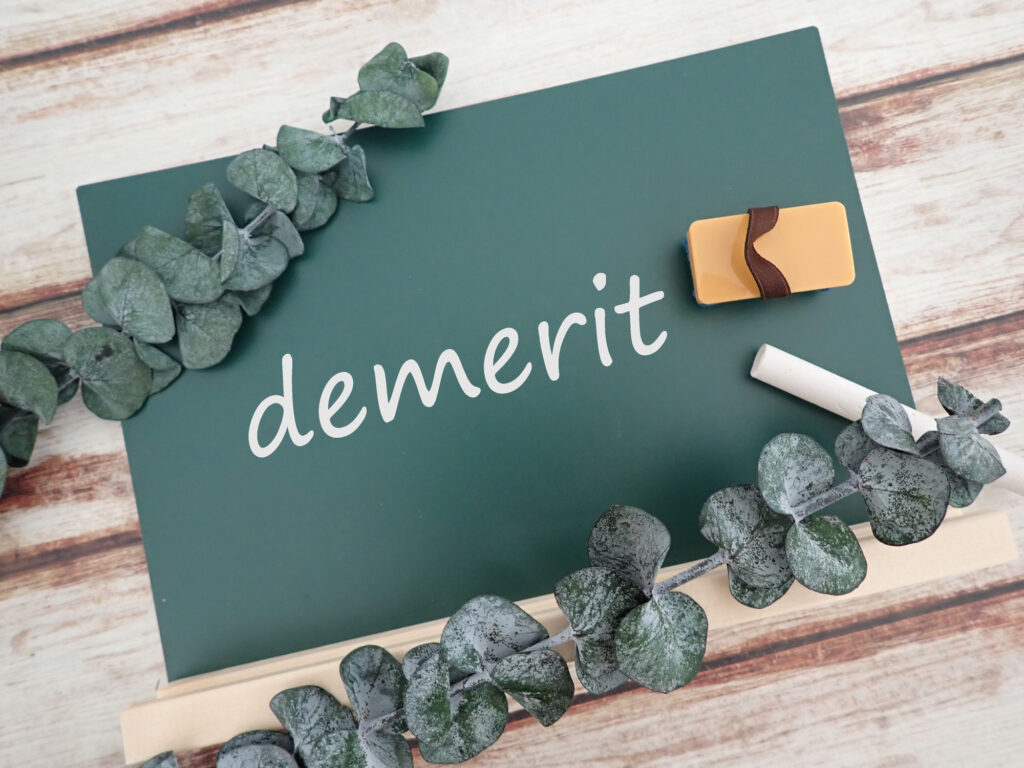
吹き抜けのある家は多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。以下では、吹き抜けの家に関する代表的なデメリットについてくわしく解説します。
- 建物の強度に不安が残る
- 冷暖房効率が低下するおそれがある
- 音や臭いが広がりやすい
- 掃除・メンテナンスが難しい
上記4点について、くわしく見ていきましょう。
建物の強度に不安が残る
吹き抜けを設けることで、通常の壁や天井の面積が減少し、構造的な強度に影響を与える場合があります。特に耐震性の観点から、吹き抜け部分が広がることで、建物全体の耐久性や揺れに対する耐性が低下することは、大きなデメリットの1つです。
また、吹き抜け部分が広いと、上部の重量を支えるために壁や柱の配置が限られ、設計上の制約が出てくることも考えられます。
冷暖房効率が低下するおそれがある
吹き抜けは空間が広がることによる、冷暖房の効率が低下することもデメリットです。
特に冬場は、暖かい空気が上へと移動しやすく、リビングや居住空間の下階が十分に暖まらない場合があります。逆に、夏場は冷房が効きづらく、広い空間を冷やすために多くのエネルギーが必要になります。
音や臭いが広がりやすい
吹き抜けは空間が一続きになるため、音や臭いが広がりやすくなります。
例えば、リビングでの会話やテレビの音が上階に響きやすく、2階で作業や休息を取っている場合には騒音問題が生じることがあります。
掃除・メンテナンスが難しい
吹き抜け部分の天井や高い窓の掃除は、日常的に行うには困難です。
高い位置にある窓や照明器具に手が届きにくく、定期的にメンテナンスを行う際には、特別な器具やプロのサービスが必要になる場合があります。
特に窓が多い場合は、汚れが目立ちやすくなるため、掃除の頻度を高くする必要があります。
吹き抜けのある家で後悔しないためのポイント

ここからは、吹き抜けのある家で後悔しないためのポイントについて解説します。
- 耐震性を第一に考える
- 家全体の断熱性能を高める
- エアコンの台数や位置を工夫する
- シーリングファンで空気を循環させる
順番に見ていきましょう。
耐震性を第一に考える
吹き抜けのある家は、通常の家よりも壁や天井の面積が少なくなるため、耐震性に不安が生じることがあります。そのため、建築設計の段階でしっかりと耐震性を考慮した構造にすることが大切です。
具体的には、吹き抜けの周囲に強度の高い梁や柱を配置し、建物全体の構造が強固になるように設計することが重要です。また、耐震等級が高い建材や構造を選ぶことで、地震に強い家を実現できます。
家全体の断熱性能を高める
吹き抜けのある家は、特に空間が広いため、冷暖房効率が悪くなりやすいです。これを防ぐためには、家全体の断熱性能を高めることが重要です。
断熱材を適切に配置し、壁や天井などの断熱強化を行うことで、外部からの熱の出入りを抑え、冷暖房効率を向上できます。
エアコンの台数や位置を工夫する
吹き抜けのある家では、冷暖房効率が低下しがちなため、エアコンの配置や台数にも工夫が必要です。
一般的に、1台のエアコンで広い吹き抜け空間をカバーするのは難しいため、必要に応じて複数のエアコンを設置することが望ましいといえます。また、エアコンを効率的に使うためには、空気の流れを考慮した設置がおすすめです。
シーリングファンで空気を循環させる
吹き抜け空間では、暖かい空気が上に溜まりやすく、下の階が十分に暖まらないという問題が発生しがちです。この問題を解決するために、シーリングファンを設置することが効果的です。
シーリングファンは、空気を上下に循環させることで、暖かい空気を下に送れます。部屋全体を均一に暖めたり、冷たい空気を効率よく下階に届けたりする効果があります。
特に冬は、シーリングファンを逆回転させることで、天井付近に溜まった暖かい空気を下に押し戻し、効率的に部屋全体を暖めることが可能です。
吹き抜けのあるおしゃれな家を実現するアイデア

ここからは、吹き抜けのあるおしゃれな家を実現するアイデアについて解説します。
- 吹き抜け部分に階段を設置する
- 高窓・天窓を設置する
- おしゃれな照明器具を採用する
上記の3点について、順番に見ていきましょう。
吹き抜け部分に階段を設置する
吹き抜けの空間にデザイン性のある階段を配置することで、視覚的なアクセントを加え、家全体の雰囲気をスタイリッシュに演出できます。
階段が吹き抜けに面することで、家全体に広がりが生まれ、空間の一体感を強調できます。ここでは、実際の施工例をご紹介します。
<開放的に暮らす、吹き抜けリビングの家(伊勢崎市)>

※出典:開放的に暮らす、吹き抜けリビングの家【伊勢崎市】|翼創建
吹き抜け部分に階段を設置することで、より広く、おしゃれな空間を演出できます。オブジェのような鉄骨階段が、空間のポイントになっています。
高窓・天窓を設置する
吹き抜け部分に高窓や天窓を設置することで、自然光をより効果的に取り入れ、明るく開放的な空間を実現できます。
特に天井が高くなる吹き抜けには、壁面の上部に大きな窓を配置するのがおすすめです。自然光が昼間の間、長時間差し込み、家全体が明るくなる効果があります。
ここでは、実際の施工例をご紹介します。
<吹き抜けのあるグレイッシュな家(邑楽郡邑楽町)>

※出典:吹き抜けのあるグレイッシュな家【邑楽郡邑楽町】|thinks 翼創建 – 群馬・栃木のデザイン住宅・注文住宅
高窓を設置することで、自然光が入り明るい空間になっています。オーダーならではの洗練されたデザインで、見た目は非常にスタイリッシュです。
おしゃれな照明器具を採用する
吹き抜け空間では、照明が空間全体の印象を大きく左右します。
おしゃれな照明器具を選ぶことで、吹き抜けの高さや広さを活かし、視覚的なアクセントを加えられます。
例えば、大きなシャンデリアやペンダントライトを中心に吊るすのがおすすめです。吹き抜けの中央にデザイン性の高いフォーカルポイントを作り、空間全体を引き締められます。
吹き抜けのある家に関するよくある質問

ここからは、吹き抜けのある家に関するよくある質問を紹介します。
- 吹き抜けのある家で後悔しがちな失敗事例は?
- 吹き抜けとハーフ吹き抜けの違いは?
- 吹き抜けのある家にすると部屋数は減る?
順番に見ていきましょう。
吹き抜けのある家で後悔しがちな失敗事例は?
吹き抜けのよくある失敗事例として、冷暖房の効率が悪いことが挙げられます。
吹き抜け部分の天井が高いことで、特に冬場に暖房の効きが悪くなり、部屋が暖まりにくいという声が多くあります(※)。暖かい空気は上に溜まりやすいため、下階が十分に暖まらず、暖房費がかさむことがあるでしょう。
※一般的な傾向であり、翼創建のお客様の事例ではありません
吹き抜けとハーフ吹き抜けの違いは?
吹き抜けは、天井まで完全に開放された空間を指します。通常、1階と2階の間に床や壁がなく、リビングなどの空間を広々と感じさせるために取り入れられます。
ハーフ吹き抜けは一部だけ吹き抜けにした設計です。例えば、リビングの一角や階段部分にのみ吹き抜けを設けることで、空間に開放感を持たせながらも、上下階のプライバシーや冷暖房効率を維持できます。
天井全体が開かれているわけではないため、部屋のレイアウトに柔軟性があり、部屋数を確保しやすい点も特徴です。
吹き抜けのある家にすると部屋数は減る?
吹き抜けのある家では、通常の設計に比べて床面積を削ることになるため、結果的に部屋数が減る場合があります。吹き抜け部分を確保することで、そのエリアには2階の床を設けられず、結果として居室のスペースが減少することになるためです。
ただし、設計次第では効率的な空間の使い方が可能です。例えば、ハーフ吹き抜けを取り入れることで、部屋数を減らすことなく、開放感を維持できます。
吹き抜けのある家は快適に過ごせる工夫が大切
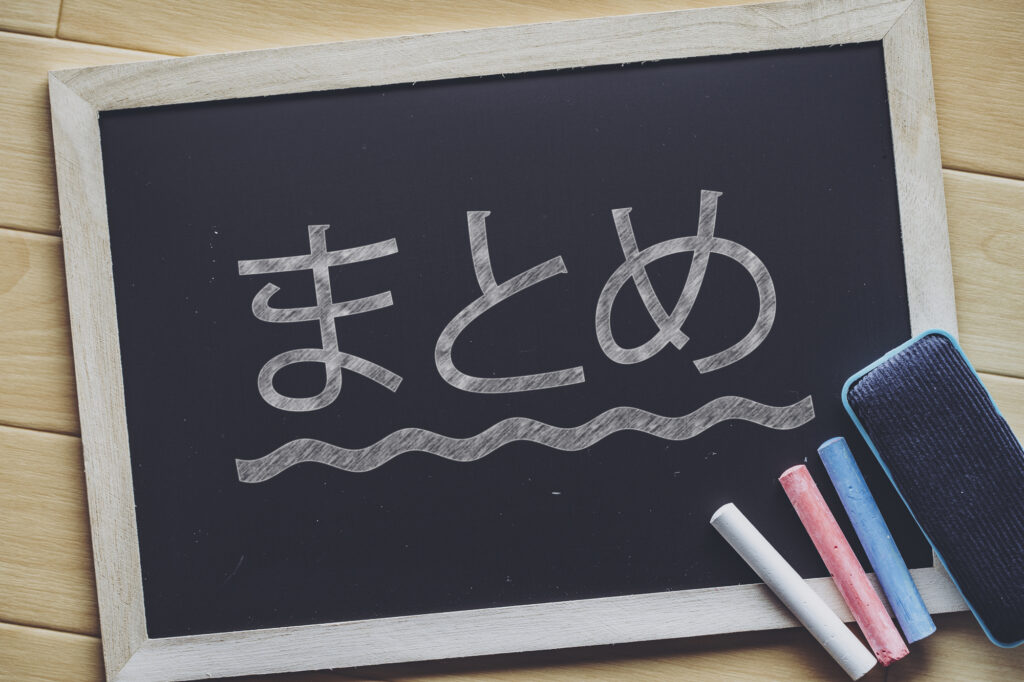
この記事では、吹き抜けのある家のメリット・デメリットについて解説しました。
吹き抜けのある家は、自然光を取り入れやすく、部屋全体が明るくなることや、風通しが良くなるなどのメリットがあります。ただし、冷暖房効率が低下するなどのデメリットがあることには、注意が必要です。
吹き抜けを検討する場合は、これらのメリット・デメリットを吟味することが重要です。
 thinks 翼創建 家づくりコンテンツ
thinks 翼創建 家づくりコンテンツ 








